私には4人の子どもがいるのですが
保育園に通うときに
一番戸惑ったのが”食器の準備”でした。
ある園では全部そろえてくれるのに
別の園では家庭でスプーンやフォークまで準備しないといけない。
さらに、年齢によってルールが変わるので
最初はとても混乱しました。
同じように悩んでいるママやパパのために、
今回は保育園食器の選び方と失敗しないポイントを
私の経験を交えて紹介しますね。
この記事を読めば、入園準備で食器選びに迷わず安心できるはずです。
保育園食器選び方の基本ルールを徹底解説

保育園によって
子どもが使う食器の準備はバラバラです。
園がすべて用意してくれるところもあれば
コップやスプーンなどの一部を
家庭で揃える必要があるところもあります。
まずは、入学説明会や配布されるしおりで
園のルールを確認しましょう。
私の子ども達が通っている園では
4歳児までは家庭で食器を用意する
必要がありせん。
園がすべて準備してくれるため
親が持たせるのは「食事用のエプロン」と
「食事後に口を拭くためのミニタオル」だけでした。
ただし、5歳児からはお箸の練習が始まるため
「スプーン・フォーク・箸がセットになった食器」
を用意する必要がありました。
このように、年齢によって準備するものが
変わる保育園もあります。
どの園でも共通して重視されるポイントは
下記のような内容になります。
- 安全性(角が丸く、子どもが安心して使える)
- 割れにくさ(プラスチックやメラニン製など)
- 扱いやすさ(軽い・洗いやすい・収納しやすい)
- 名前の記入(紛失防止のため)
逆に、ガラスや陶器など割れる食器は
危険なので避けられるし
キャラクター物を禁止にしている園もあります。
このように「園によって違う」
「年齢によって違う」という点を
知っておくだけで食器の選び方の不安がグッと減りますよ。

たくさん種類があるから
どれを選べばいいか迷いそう。
保育園食器選び方|素材ごとのメリットとデメリット

園から「食器はご家庭で準備してください」
と言われたとき
「どんな素材がいいの?」「大きさは?」
「キャラクター付きでも大丈夫?」と
いろいろ迷いますよね。
子どもが毎日使うものだから
安全で使いやすい食器を選びたい。
家庭用と違って
「落としても割れにくいもの」
「子どもが持ちやすいもの」
「管理がしやすいもの」と
条件を言われる場合があります。
さらに園によっては
「電子レンジ対応不可」
「名前シールを必ず貼ること」など
細かい指定があることも。
ここでは、どの園でも共通して役立つ
食器の選び方のポイントをまとめました。
これを参考にすれば、入園準備で迷わず
安心して食器を選べますよ。
素材で選ぶ
私も保育園用の食器を準備したとき
「どの素材なら安心?」
「すぐに傷ついたりしないかな?」と
わからないことが多くて悩みました。
きっと私と同じように
迷っているママやパパも多いはず。
そこで、子どもが毎日安心して使えるように
素材ごとの特徴やメリット・デメリットを
わかりやすく表にまとめました。
| 素材 | メリット | デメリット | 向いているケース |
| プラスチック | ・軽くて扱いやすい ・安くて買い替えやすい | ・傷がつきやすい ・色移り、曇りやすい | ・軽さとコスパ重視したいとき |
| メラニン | ・丈夫で割れ難い ・デザインが豊富 | ・電子レンジ不可が多い | ・保育園で指定される場合や長く使いたいとき |
| ステンレス | ・匂い、色がつきにくい ・衛生的で長持ち | ・熱くなりやすい ・口当たりを嫌がられる可能性あり | ・コップや長期利用を考えているとき |
| 竹・木製 | ・ナチュラルで見た目がかわいい ・子どもの食欲up効果も | ・水に弱い ・お手入れが必要 ・耐久性に劣る | 家庭用で、雰囲気を楽しみたいとき |
サイズ・形で選ぶ
食器は素材だけでなく、サイズや形も大切です。
子どもの年齢や手の大きさに合っていないと
「持ちにくい」「食べにくい」といった状態
になります。
毎日、使うものだからこそ
子どもが自然に使いやすい形を選びましょう。
子どもの手に合った大きさ
小さな子どもには
直径10~12㎝程度のお皿や
浅めで軽いものがおすすめ。
大きすぎると持ちにくく
食事中に疲れてしまい
途中で寝てしまうことも。
私の家では、子ども用の軽くて
小さなお茶碗を重宝しています。
お気に入りの食器があれば
子どもが喜んで楽しく食事してくれますよ。

子どもはデザインが可愛いものがいいのかな?
深さのあるお皿
汁物やカレー・シチューなどは
スプーンですくいやすいように
角が丸い食器を選ぶと食べやすいです。
また、自分で食べる練習にもなります。
仕切り皿

ご飯・おかず・果物を分けて盛りつけられるので
小食の子どもでも食べやすいです。
私の家では、子どもが食べ物で遊んだので
仕切り皿は使いませんでした。
しかし、保育園によっては
1つのプレートで食事ができる
仕切り皿を指定される場合があるみたいです。
取っ手付きのコップやお椀
小さな子どもは取っ手があると持ちやすく
こぼしにくいです。
例えば、コップだと両手でとってを握って
飲むので、ひとりで飲めるようになるのが早いです。
慣れてきたら、少しずつ取ってなしに
移行してあげるといいですよ。
保育園食器選び方で重視するべき安全チェックリスト

保育園で使う食器を選ぶとき
安全性は重視して考えたいポイントになります。
毎日使うものだから
「子どもに安心して使わせられるか」も大切ですが
集団生活で食器を使ったとき
万が一、床に落としても周りにいる先生や友だちが
ケガをしないかも視野に入れて考えたいですよね。
ここでは、安全性について詳しく解説します。
私の家では、子どもが4人いるので食器選びで
一番重視しているところになります。

どんな食器が安全に使えるのかな…
BPAフリーかどうか
プラスチック製やメラミン製の食器を選ぶときは
「BPAフリー」の表示をチェックしましょう。
最近では、BPAがごく微量ながら
食品や飲み物に移る可能性があることを
指摘されています。
長期的に摂取すると
子どもの発達や健康に影響が
出るかもしれないと言われています。
なので、「BPAフリー」と表示された商品が
多く販売されるようになり
子どもに安心して使えるのでおすすめです。
角やフチの形状

角が鋭いと、子ども皮膚は大人と比べて
柔らかいので、口や手を切る恐れがあります。
なので、丸みのあるデザインの食器を選ぶ
と安心して使えますよ。
落としても割れにくい素材
保育園では子どもが食器を落とすことが
日常茶飯事です。
陶器やガラスは落としたとき
破片が飛び散り危険なので避けましょう。
子どもの食器選びは、割れにくい素材の
プラスチックやメラミン製を選ぶといいですよ。

落としてもケガをしないものがいいな。
耐熱性・耐冷性
電子レンジや食器洗い機に
対応しているかどうかも大切です。
熱で変形したり、ヒビが入ったりすると
気づかず使っていたら
子どもがケガをすることも…。
対応温度を確認してから商品を購入しましょうね。
保育園食器選び方|軽くて管理しやすい食器が便利

食器は毎日使うので
扱いやすいかどうかも大切です。
少しの工夫で毎日の家事がラクになります。
また、扱いやすい食器を使うことにより
子どもがひとりで食事ができるようになり
親の負担が減りまよ。
軽くて持ちやすい
子どもが自分で食べやすいだけでなく
毎日の荷物を用意するのがラクになります。
子どもが自分で荷物を持ってくれるのなら
多少、食器が重たくても負担になりません。
しかし、子どもが2歳になるくらいまでは
ママやパパが子どもの代わりに
荷物を持つことになります。
また、軽い食器は洗ったあと
乾きやすいのが嬉しいポイントです。
重ねやすい
食器を重ねて収納できるタイプは
持ち運びもしやすく、食器棚のスペースを
あまり使わないので便利です。
保育園によっては
「持ち帰り用にコンパクトにまとめる」
必要があります。
洗いやすい形状

毎日使うものなので
シンプルで洗いやすいものがおすすめ。
複雑な形だと、スキマに汚れが溜まりやすく
洗うのに手間がかかります。
なので、シンプルな形のものだと
汚れが溜まりにくいので衛生的に使えます。

子どもが食べ物で遊ぶから
食器はシンプルなものがいい!
耐久性
一度、食器を購入したら
買い替えるのも大変なので
長期間使いたいですよね。
洗っても劣化しにくい素材を選ぶこと
をおすすめします。
選ぶ素材によっては
表面がすぐに傷だらけになるので
衛生面のことも考えて食器を選びましょう。
保育園食器選び方まとめ|失敗しないためのチェックポイント

- 保育園の食器ルールは園によって大きく違う
- 年齢によって準備するものが変わる
- 食器を選ぶときは
素材・サイズ・安全性・扱いやすさの
4つをチェック - 子どもの手の大きさに合ったサイズや
取っ手付きなどの形状に配慮する - 安全面をしっかり確認する
- 実際に使ってみると「便利だった点」や
「失敗した点」がわかるので、経験も参考になる

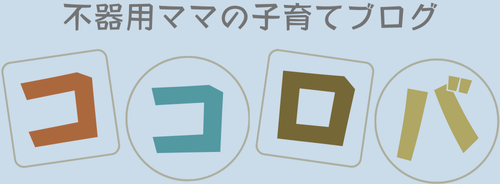


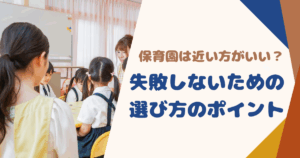

コメント